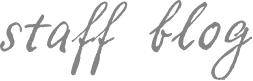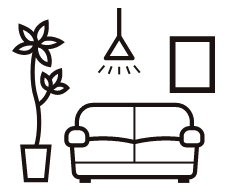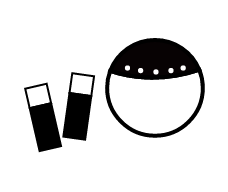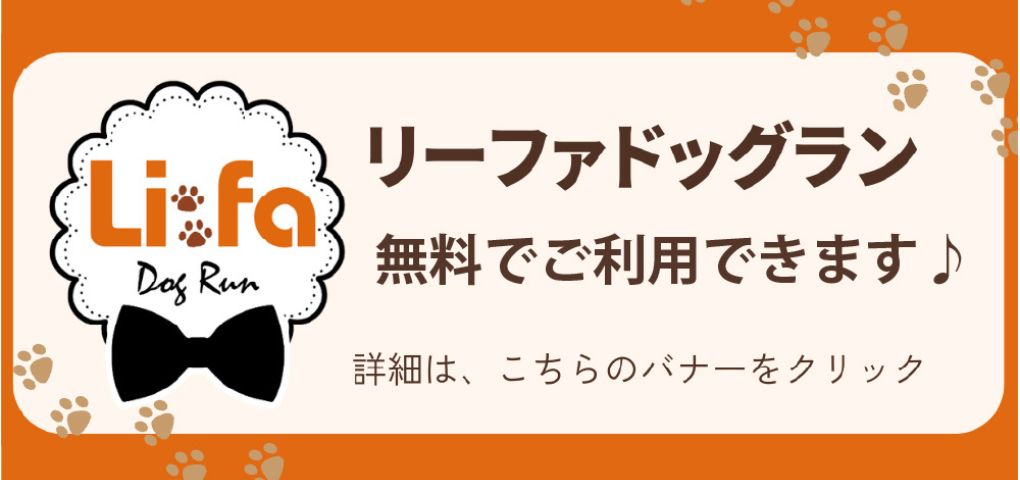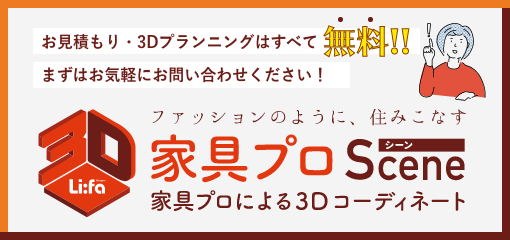メイクやお肌のお手入れはどこで??ドレッサーで!!
皆様、こんにちは!
皆様は普段、お化粧やお肌のお手入れをするときに鏡台をお使いになりますか?
今では、ドレッサーと呼ぶ方が多いかもしれませんね!( ・ω・)
昔から嫁入り道具の1つとして購入される事が多く、お母様からお子様へと代々引き継がれて、使用される場合もあります。
そもそも鏡台の起源は、池などの水面に姿かたちを映し出す、水の鏡だとされています。
その後、弥生時代、古墳時代にかけて、銅鏡が中国から持ち込まれました。
その時はお化粧をするためでなく、呪術用や祭祀用具として使われていました。
平安時代になり、貴族たちの間でお化粧をする習慣が起こり、鏡を五本脚で支える丈の短い柱に掛けたことが鏡台の始まりと言われています。
今、皆さんが使っているようなドレッサーの形に近い鏡台は、室町時代に登場しました。
ちなみに、「ドレッサー」と名付けられたのは、昭和34年頃だそうです。
鏡台(ドレッサー)にも様々な種類がありますので、ご紹介します(^^)/
▽一面鏡タイプ

付いている鏡が1枚で、鏡が縦長だったり、丸い大きめのものだったり特徴的です!(*’▽’)
ドレッサーによっては、姿見になるものもございます。
▽三面鏡タイプ

三面鏡は、正面と左右に鏡が1枚ずつあるので、ヘアアレンジやメイクの左右のバランス、全体のバランスを同時に確認することが出来ます。
また、三面鏡にも種類があり、本三面鏡と半三面鏡があります。
上の写真のドレッサーは、半三面鏡です。
本三面鏡と半三面鏡は、
鏡を閉じた状態と鏡を開いた状態の鏡の大きさで見分ける事が出来ます。
(1枚目:本三面鏡、2枚目:半三面鏡)


本三面鏡は、正面と左右にある鏡の大きさがすべて同じで、
半三面鏡は、左右の鏡の大きさが正面の鏡の半分の大きさになっています。
さらに七分三面鏡という種類もあり、


七分三面鏡は、鏡を閉じたときに
閉じた鏡の見た目が7:3になることから、そう呼ばれています。
左右の鏡の大きさが、本三面鏡と半三面鏡の中間ぐらいの大きさなので、
「本三面鏡まで、鏡が大きいのはいらないけど…半三面鏡の鏡だと小さいな…」
と思ってらっしゃる方にピッタリです♪
また、ドレッサーのスツールやイスにも特徴があり、イスの横にティッシュペーパーを入れる事が出来るものもございます!

ちょうど、腕を下した位置にあるので取りやすく、
わざわざ立ち上がってティッシュペーパーを取りに行く手間が省けます(^^)
お化粧をする時などは近くにティッシュペーパーがあるとすごく便利ですよね♪
その他にも、ドレッサーには便利な機能がたくさんありますので、気になる方は是非店頭にいらしてください。
只今、ドレッサーフェア開催中!!
お買い得なドレッサーをたくさんご用意しております。
皆様のご来店をお待ちいたしております。
タムラ